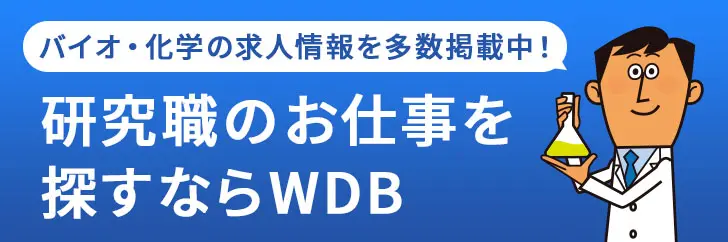概要
本来は単一、あるいは同一であったものが、複雑化したり、異質化したりしていくさまを「分化」と言います。発生の過程では、1つの受精卵から分裂して分かれた胚細胞が、やがて筋細胞、神経細胞、上皮細胞等のように異なった機能を持つ細胞になる現象を「細胞分化」といいます。
また、発生初期の胚細胞は、様々な種類の細胞になる潜在的な能力を持っており、このような状態を、まだ分化していないという意味で「未分化細胞」と呼んでいます。
性質
通常、細胞分化は不可逆であり、受精卵の状態では全ての組織へ分化できる全能性を持っていますが、分化が進むと分化できる細胞の種類が決まってしまいます。一度分化した細胞が他の細胞にならない不可逆性を持つ大きな要因としては、分化後の細胞に必要な遺伝子以外の遺伝子の塩基配列がメチル化され、発現ができなくなり遺伝情報を失うといったことが分かっています。
活用例
iPS細胞とは
人間の皮膚等の体細胞に極少数の因子を導入し、培養することによって、様々な組織や臓器の細胞に分化する能力とほぼ無限に増殖する能力をもつ多能性幹細胞に変化します。この細胞を人工多能性幹細胞(induced pluripotent stem cell:iPS細胞)と呼びます。名付け親は、世界で初めてiPS細胞の作製に成功した京都大学の山中伸弥氏です。
体細胞が多能性幹細胞に変わることを、専門用語でリプログラミングと言います。山中氏のグループが見出したわずかな因子でリプログラミングを起こさせる技術は、再現性が高く、また比較的容易であり、幹細胞研究におけるブレイクスルーと呼べます。

iPS細胞の活用
iPS細胞は、病気の原因解明、新薬開発、細胞移植治療等の再生医療に活用できると考えられています。
再生医療とは、病気や怪我等によって失われてしまった機能を回復させることを目的とした治療法で、iPS細胞がもつ多分化能を利用して様々な細胞を作り出し、例えば糖尿病であれば血糖値を調整する能力をもつ細胞に、神経が切断されてしまうような外傷を負った場合には、失われたネットワークをつなぐことができるように神経細胞を移植する等のケースが考えられます。
一方、難治性疾患の患者の体細胞からiPS細胞を作り、それを神経、心筋、肝臓、膵臓等の患部の細胞に分化させ、その患部の状態や機能がどのように変化するかを研究し、病気の原因を解明する研究も期待されています。例えば、脳内にある神経細胞が変化して起こる病気は、外側からアクセスすることが難しく、また変化が進んでしまった細胞からは、正常な状態がどうであったかを推測することが難しいとされてきました。iPS細胞を用いることで、こうした研究が飛躍的に進む可能性があります。
また、その細胞を利用すれば、人体ではできないような薬剤の有効性や副作用を評価する検査や毒性のテストが可能になり、新しい薬の開発が大いに進むと期待されています。そして、安全性が確保されたならば、患者由来のiPS細胞から分化誘導した組織や臓器の細胞を移植する細胞移植治療のような再生医療への応用も期待できます。
iPS細胞の課題点
病気や怪我で失われた細胞をiPS細胞から作製して移植する、細胞移植治療の実現を目指した研究が国内外で行われています。iPS細胞を用いた再生医療における安全性の課題として、腫瘍が形成されるのではないか、という懸念がありました。これまで、世界中でiPS細胞の安全性の向上に関する研究が行われてきました。とりわけ、CiRAでは研究所をあげてこの課題に取り組んできました。その結果、懸念された課題を解決し、大幅に安全性を高めることに成功しています。
iPS細胞が腫瘍化するメカニズムは、大きく分けて2つの理由が考えられてきました。1つは細胞に導入された初期化因子が再活性化すること、あるいは人工的に初期化因子を導入するため、もともとの細胞がもつゲノムに傷がつくことで、iPS細胞が腫瘍化してしまう、というものです。これについては、再活性化を起こさない最適な初期化因子が探索され、また、初期化因子が細胞の染色体に取り込まれない(ゲノムに傷をつけない)iPS細胞の作製方法が開発されています。もう1つは、未分化細胞(目的の細胞に変化しきれていない細胞)が残存すること等によって引き起こされる、テラトーマと呼ばれる奇形腫(良性腫瘍)の形成です。これについては、iPS細胞の増殖や分化に関する研究が進められており、着実に成果をあげつつあります。
歴史的背景
発生機構の解明
18世紀までは生物の体はあらかじめ完全な形で形成されているという前成説が有力でした。顕微鏡を作成したレーウェンフック氏は様々な動物の精子を観察し、精子の中には完全な形をしたホムンクルスが入れ子になっているという前成説を支持していました。これに対して、ヴォルフ氏は1759年にニワトリ卵にいて器官の原基が小さい球体として生じる詳細を説明して、最初から器官の形が存在する訳ではないことを明確に述べました。これが後成説の成立と見なされ、その後19世紀には後成説がほぼ認められるようになりました。
実質的なこの分野での発展は、ウィルヘルム・ルー氏による実験発生学によって始まります。ルー氏は発生の各段階の胚に様々な刺激を与え、それによる胚発生の変わり方を見ることで、発生機構を解明しようとしました。例えば、彼の実験で有名なものに、カエルの卵の二細胞期に、片方の割球(細胞のこと)を加熱した針で殺す、というものがあります。その結果、残りの割球は発生を続け、半分の形の胚ができました。このことから、彼は第一卵割の時に胚の左右の分化が起きると結論づけています。この実験は、割球を取り除くと完全な胚が生じるため、この結論は正しくありませんが、このような方法で発生の仕組みに迫ろうとしたのです。
なお、彼の研究は主としてヴァイスマン氏の生殖細胞質連続説に深い関わりがあります。この説は、遺伝子のようなものが親から子へと生殖細胞を通じて伝わるという遺伝の説という側面と、その中に含まれる決定要素が卵割によって配分されることで個々の細胞の分化が決まるとする発生論の側面があり、ルー氏の実験はその当否を確かめることを目指しました。